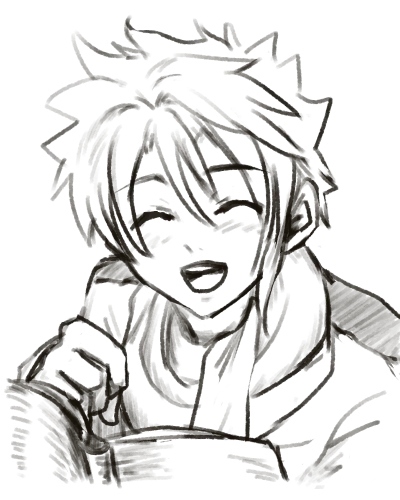10年前、父さんに連れられて、ひとりの子供がやってきた。
手を引かれて入ってきたその子供は、俺よりひとつふたつ下にみえた。
いや、それよりもまず目を引いたのが、その容姿だ。
白い肌、やわらかい薄墨色の髪。目は血の赤が透けたような不思議な色をしている。
まるでファンタジー世界の人形のようだった。
「うちで引き取ることになった」
父さんはそう告げた。
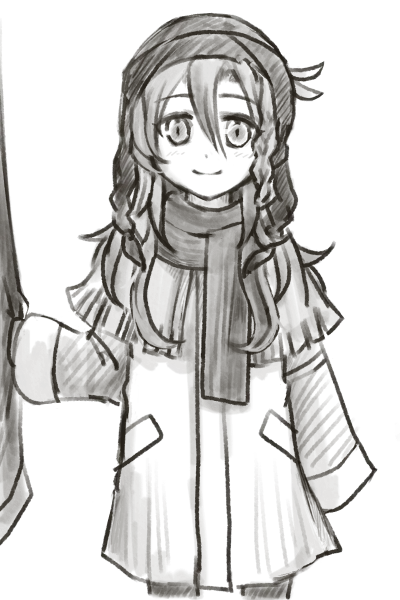
性別は男。名前はハルカ。
といっても、本名ではない。
遠い国の紛争地域で保護されたそうだ。
それにしても珍しい色をしているが、とりわけ激しい戦地での奇跡的な保護とのことで、素性が一切分からないらしい。
そして、この国の風が冷たいのだろうか、まだ秋の入口だというのに、しっかり着込んでマフラーまで巻いている。
かわいそうに、同情の念が押し寄せるも、目前の彼は俺に向かって笑いかけてきた。
それは、苦境からやっと逃れられた安堵から来るものともまた違う。
「何も憶えていないようだ…幸いというべきか」

ハルカは器用で、物覚えがよかった。
なにか新しい事を会得するたびに、彼はとびきりの笑顔を見せた。
俺は、ハルカがこの国に馴染めていることに安堵し、また、この笑顔を守ってやりたいと決意するのだった。
このまま、月日は流れ、ハルカも他の子どもと大差無い生活を送れるようになり……
俺たちは、今日も一緒に学園に通う。
大きな事件も無い、平和な日常。
この日常が、いつまでも続くものと思っていた。